2007.4.21
仩椺偊偽丄偙偙偵僪儗儈僼傽僜儔僔僪丄儊僕儍乕僗働乕儖偱弌棃偨嬋偑偁傞偲偟傑偡仩
偙傟傪廬棃婛惢昳偱墘憈偟傛偆偲偡傞偲丄1st億僕僔儑儞偟偐傎傏慖戰巿偑偁傝傑偣傫丅
偦傟埲奜偵側傝傑偡偲丄偄偒側傝僆乕僶乕僽儘僂偑昁梫偵側傞偺偱偡丅傑偨丄偣偭偐偔僽儖乕僗僴乕僾偩偐傜偲儈b丄僜b丄僔b偁偨傝偺僽儖乕僲乕僩偱枴晅偗偟偨偔偲傕丄1st億僕僔儑儞忋偱偼偙傟傜偡傜崲擄偩丄偲偄偆暻偵傇偪摉偨傝傑偡丅
乽僽儖乕僗僴乕僾側偺偵僼僅乕僉乕側姶偠偐丄慺捈乣側姶偠偺慖戰巿偟偐柍偄側傫偰偭偭乿
偦傫側偙傫側偱丄flisnuf偲偄偆儌僨儖偑惗傑傟傑偟偨丅壗偑堘偆偭偰丄壒偺攝楍偑堘偆傫偱偡丅偦傟偩偗偱偡丅
挌搙堦擭慜偔傜偄偐傜丄儔僀僽傗儗僐乕僨傿儞僌偱傕巊偭偰丄崱偱偼姰慡偵帺暘偺拞偱儗僊儏儔乕壔偟偰偄傑偡丅偦傟偱偼偳傫側傕偺側偺偐徯夘偟傑偟傚偆乣
flisnuf偺攝楍
| 寠斣崋 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 媧壒 | B | D | G | B | D | F# | A | B | D | F# |
| 悂壒 | G | C | E | G | C | E | G | Bb | C | E |
仭傑偢廬棃婛惢昳偲堘偆偺偼丄0斣寠偑偁偭偰10斣寠偑柍偄乧両偲偄偆偲偙傠偱偟傚偆偐丅
傑偨7斣悂壒偵偼撲偺Bb壒偑偁傝傑偡丅偙傟偵傛偭偰寠偑偢傟崬傒丄係丆俆斣偲俉丏俋斣偑摨偠壒偺巇慻傒偵側偭偰偄傑偡丅
僴乕儌僯僇偺僶乕僞乕岠壥偺惈幙忋丄偙傟偵傛偭偰俉丆俋斣偺悂壒儀儞僪偼柍偔側傝丄媡偵媧壒儀儞僪偑壜擻偵側傝傑偡丅
偙偺儌僨儖偼嬌傔偰崅壒晹暘偺姶妎偑廬棃婛惢昳偲堘偄傑偡丅10斣寠傗廬棃偺9斣悂壒G壒偑梸偟偐偭偨傝丄悂壒儀儞僪偑偟偨偄応崌偼偙偺儌僨儖偵偼岦偐側偄偺偱丄偍偲側偟偔廬棃婛惢昳傪巊偆偑椙偟偱偟傚偆偐丄丄丄丄丄
偦偺戙傢傝偲偄偭偰偼壗偱偡偑丄4斣媧壒偺僼僃僀僋丄儀儞僪偑偛偲偔丄摨偠偙偲傪9斣媧壒偺儀儞僪丄僼僃僀僋偑壜擻偵側偭偰偄傑偡丅
偙偺曈偼丄廬棃婛惢昳偱偼揔傢側偄丄偐備偄偲偙傠偵庤偑撏偔姶偠偱偟傚偆丅
側偍丄偙偺攝楍偱偡偲僆乕僶乕僽儘僂偼Eb壒偺傒偱OK偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅
埲壓丄奺億僕僔儑儞偱偺徯夘偱偡丅崱夞偼丄僆乕僶乕僽儘僂柍偟偱儊僕儍乕僗働乕儖億僕僔儑儞偑偳傟偩偗悂偗傞偺偐丅偦偺曈傪僺僢僋傾僢僾偟偰傒傑偡丅
1st億僕僔儑儞偱巊偆応崌乮KeyC乯
| 寠斣崋 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 媧壒 | B僔 | D儗 | G僜 | B僔 | D儗 | F# | A儔 | B僔 | D儗 | F# |
| 儀儞僪 | A儔 | 丂 | F僼傽 | A儔 | 丂 | F僼傽 | 丂 | 丂 | 丂 | F僼傽 |
| 悂壒 | G僜 | C僪 | E儈 | G僜 | C僪 | E儈 | G僜 | Bb | C僪 | E儈 |
仭傑偢偼偍側偠傒丠偺1St億僕僔儑儞偱偡丅
堦斣嵟弶偵0斣偑偁偭偰暣傜傢偟偄偗偳丄偲側傝偺侾斣偐傜偼偍撻愼傒偺僼傽丄儔偑儀儞僪偱乧偲偄偆宍偼廬棃偺婛惉儌僨儖偲摨偠偱偡丅
偨偩5斣9斣偑僼傽僀儕儞僌偝傟偰偄傞偺偱丄僼傽偼慡晹儀儞僪偱弌偡傛偆偵側傝傑偡丅
偙偺億僕僔儑儞偱偺悂憈姶偼丄廬棃婛惢昳偲偁傑傝曄傢傝偑偁傝傑偣傫丅
側偍丄1st億僕僔儑儞儅僀僫乕乮KeyCm乯偼僆乕僶乕僽儘僂偑弌偰偔傞偺偱擄偟偄偭偡傛丅
2nd億僕僔儑儞偱巊偆応崌乮KeyG乯
| 寠斣崋 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 媧壒 | B儈 | D僜 | G僪 | B儈 | D僜 | F#僔 | A儗 | B儈 | D僜 | F#僔 |
| 儀儞僪 | A儗 | 丂 | F#僔 | A儗 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |
| 悂壒 | G僪 | C僼傽 | E儔 | G僪 | C僼傽 | E儔 | G僪 | Bb | C僼傽 | E儔 |
仭懕偄偰2nd偱偡丅傕偲傕偲偙偺億僕僔儑儞偑僼傽乕僗僩偱偄偄偠傖傫丄偲偄偆偺傪尦偵嶌傜傟偨偺偱偙傟偑堦斣墘憈偟傗偡偄傛偆偵弌棃偰偄傑偡丅
廬棃婛惢昳偱墘憈偟偰偄偔偲5斣媧壒偱儊僕儍乕僗働乕儖偺僔偺壒偑弌傑偣傫偑丄偙傟偼僼傽僀儕儞僌偟偰偁傞偙偲偵傛傝偒偪傫偲偟偨儊僕儍乕僗働乕儖偑僨僼僅儖僩偱巇崬傑傟偰偄傑偡丅
僽儖乕僗側偳偱F壒乮僔b乯偑梸偟偄偲偒偼媡偵儀儞僪偱弌偡偲偄偆僗僞僀儖偱偡丅
偄傢偢傕偑側丄僽儖乕僗梫慺傪崅傔傞偨傔偵儈僜僔壒偑媧壒懁偵廤傑偭偰偄偰丄儀儞僪偑壜擻偵側偭偰偄傑偡丅
傑偨僽儖乕僗偵偍偄偰偼丄3斣偺僴乕僼儀儞僪Bb壒傪傛偔巊偄傑偡偑丄8斣悂壒偵偍偄偰傕Bb壒偑偁傞偺偑偙偺儌僨儖偺摿挜偱丄偙偺壒堟偱傕廫暘僽儖乕僕乕側僼儗乕僘傪壧偆帠偑弌棃傑偡丅
0斣寠偑偁偭偨傝丄摿挜揑側晹暘傕偁傝傑偡偑丄婎杮揑偵偼偙傟偼傕偭偲傕億僺儏儔乕側僼傽僀儕儞僌偱偡偹丅僇儞僩儕乕僠儏乕儞偲傕尵偄傑偡丅
側偍丄2nd億僕僔儑儞儅僀僫乕乮Gm乯傕堦売強僆乕僶乕僽儘僂偑弌偰偔傞偱偡偑丄堦売強偩偗側偺偱Gm偺嬋傕偙偺億僕僔儑儞偱悂偗偰偟傑偆帠偑偁傝傑偡丅
3rd億僕僔儑儞偱巊偆応崌乮KeyD乯
| 寠斣崋 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 媧壒 | B儔 | D僪 | G僼傽 | B儔 | D僪 | F#儈 | A僜 | B儔 | D僪 | F儈 |
| 儀儞僪 | A僜 | C#僔丂 | F#儈 | A僜 | C#僔 | 丂 | 丂 | 丂 | C#僔 | 丂 |
| 悂壒 | G僼傽 | 丂 | E儗 | G僼傽 | 丂 | E儗 | G僼傽 | 丂 | 丂 | E儗 |
仭偙偙偐傜偑廬棃婛惢昳偱偼巊梡昿搙偺掅偐偭偨巊偄曽偱偡丅偙偺攝楍側傜偱偼偱偡偑丄嬋偵傛偭偰偼偙偺億僕僔儑儞偑妶偒傑偡丅
攝楍傪尒傑偡偲丄4斣媧壒偐傜偺攝楍偑2nd億僕僔儑儞偲丄摿偵儕乕僆僗僇乕儌僨儖偺儊儘僨傿儊乕僇乕偲崜帡偟偰偄傑偡偺偱丄暤埻婥偼媅帡揑側2nd億僕僔儑儞偵側傝傑偡丅
僔偺壒偩偗婥傪晅偗傟偽2nd偺姶妎偐傜堏峴偟傗偡偔側偭偰偄傑偡丅廬棃婛惢昳偱偼壒偺攝楍偵傛傝偙偺億僕僔儑儞偼儅僀僫乕偵側傝傑偡偑丄偙偺儌僨儖偼偦偺姶妎偱悂偔偲儊僕儍乕僽儖乕僗偵側傝傑偡丅
儊儘僨傿傪偟偭偐傝丄偒偭偪傝偲弌偟偨偔偰丄偝傜偵2nd揑側僼傿乕儖傪媮傔偨偄帪偵僴儅傞億僕僔儑儞偵側傞偱偟傚偆丅
傫偱丄儈b僜b僔b傕壜擻側傫偱偡偹丅
摿偵嬋拞偵4搙儅僀僫乕僐乕僪偑弌偰偒偰丄偦偺峔惉壒偑儊儘僨傿偲偟偰弌偰偒偰丄偙偄偮偼偼偢偣偹偊両偲偄偆帪偵栶棫偮億僕僔儑儞丄丄丄丄偐側丅
偝傜偵尵偊偽丄崱夞徯夘偡傞億僕僔儑儞偺拞偱桞堦丄儊僕儍乕僗働乕儖偑悂偗偰丄偦偺拞偱僽儖乕僗僼傿乕儕儞僌偁傆傟傞儈b僜b僔b偑壜擻偱丄偝傜偵暯峴挷偱偁傞儅僀僫乕僗働乕儖丄偟偐傕僴乕儌僯僢僋儅僀僫乕傪娷傓嶰庬偺儅僀僫乕偑慡晹弌棃傞偭偮乕枩擻億僕僔儑儞側傫偡偹丅
僆乕僶乕僽儘僂偼柍偟丄儀儞僪偺傒丄偱僕儍僘傪傗偭偰傒偨偄偲偄偆恖偵偼枹棃偑偁傞丄丄丄偐側丅
3rd億僕僔儑儞儅僀僫乕乮Dm乯偼壜擻偱偡丅廬棃婛惢昳偺僒乕僪億僕僔儑儞乮儅僀僫乕偲偄偆偐僪儕傾儞乯傕壜擻偱偡丅
4th億僕僔儑儞偱巊偆応崌乮KeyA乯
| 寠斣崋 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 媧壒 | B儗 | D僼傽 | 丂 | B儗 | D僼傽 | F#儔 | A僪 | B儗 | D僼傽 | F#儔 |
| 儀儞僪 | A僪 Ab僔 | C#儈 | F#儔 | A僪 Ab僔 | C#儈 | 丂 | Ab僔 | 丂 | C#儈 | 丂 |
| 悂壒 | 丂 | 丂 | E僜 | 丂 | 丂 | E僜 | 丂 | 丂 | 丂 | E僜 |
仭僒乕僋儖僆僽僼傿僼僗偱尵偆偲偙傠偺4斣栚偵懏偡傞偙偺億僕僔儑儞偼丄偝偡偑偵偙偙傑偱棃傞偲儀儞僪偑懡偊偊偊偊偊側偀丄丄丄丄偲偄偆姶偠偱偡偹丅丅丅
偙偺億僕僔儑儞偼廬棃婛惢昳偱尵偆偲偙傠偺僫僠儏儔儖儅僀僫乕億僕僔儑儞丄傑偨偼1st億僕僔儑儞偺暯峴挷偲偟偰傛偔墘憈偝傟傞丄傕偭偲傕億僺儏儔乕側儅僀僫乕億僕僔儑儞側偺偱偡偑丄偦傟傪儊僕儍乕偱傕悂偔偲偙偆側傝傑偡丅
側偍丄儅僀僫乕偱傕悂偔偙偲偼壜擻偱偡丅1st億僕僔儑儞傪儔偐傜巒傔偨宍偑僜儗偱偡丅
儈b僜b僔b偼丠偲峫偊傞偲丄幚嵺偙偺億僕僔儑儞偱僽儖乕僗晽枴傪墘憈偡傞偺偼戝曄偱丄偳偪傜偐偲偄偆偲儅僀僫乕僽儖乕僗晽枴偺枴晅偗偵側傞傗傕抦傟傑偣傫丅傑偀曣懱偑儅僀僫乕僗働乕儖側偺偱丅丅丅
偙偺儊僕儍乕億僕僔儑儞拞怱偱嬋傪墘憈偡傞偙偲偼偁傑傝帋偟偰偄側偄偱偡偑丄椺偊偽僕儍僘側偳偵偍偗傞II俈側偳丄晹暘揮挷偺嵺偵梸偟偄壒偑偙偺攝楍偵偼旛傢偭偰偄傞偺偱抧枴乣偵妶桇偟偰偄傞億僕僔儑儞偐傕抦傟傑偣傫偹丅
幹懌偱偡偑丄4th億僕僔儑儞儅僀僫乕乮Am乯偼壜擻偱偡丅
12nd億僕僔儑儞偱巊偆応崌乮KeyF乯
| 寠斣崋 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 媧壒 | D儔 | G儗 | 丂 | D儔 | 丂 | A儈 | 丂 | D儔 | 丂 | |
| 儀儞僪 | Bb僼傽 A儈 | F僪 | Bb僼傽 A儈 | 丂 | F僪丂 | 丂 | 丂 | 丂 | F僪 | |
| 悂壒 | G儗 | C僜 | E僔 | G儗 | C僜 | E僔 | G儗 | Bb僼傽 | C僜 | E僔 |
仭偄偒側傝旘傫偱12th億僕僔儑儞偵側傝傑偡丅偙傟偼僒乕僋儖僆僽僼傿僼僗偱尵偆偲偙傠偺嵟屻偺億僕僔儑儞偐偮丄b宯偺夞傝乮媡夞傝乯偱偄偆偲偙傠偺擇斣栚乮1st偺師乯偵弌偰偔傞偙偲偐傜僼儔僢僩僙僇儞僪億僕僔儑儞偲傕屇偽傟傑偡丅
傛偭偰b乮僼儔僢僩乯偑堦偮偟偐偮偄偰側偄偺偱丄偙偺億僕僔儑儞偱傕儊僕儍乕僗働乕儖偑揔偊傗偡偄偺偱偡丅
幚偼偙偺億僕僔儑儞偺暯峴挷偑廬棃婛惢昳偱尵偆偲偙傠偺僒乕僪億僕僔儑儞丄偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅F偺暯峴挷Dm丄偲偄偆偙偲偱偡偹丅
廬棃婛惢昳偱偺偙偺億僕僔儑儞偼丄傑偝偵偙偺暯峴挷偺僒乕僪億僕僔儑儞偱偁傞Dm偐傜F偵揮挷偡傞嬋両偺偨傔偵偁傞懚嵼偩偭偨傝丄僆乕僶乕僽儘僂偑弌棃側偄抜奒偱偺III搙僙僽儞僗昞尰偑昁恵偺壒妝丄椺偊偽儃僢僒偲偐丄偦偆偄偭偨摿庩側埖偄偱巊傢傟偰偒傑偟偨丅
偙偺儌僨儖偱偼8悂偺Bb壒偑偁傞偨傔偒偪偭偲儊僕儍乕僗働乕儖偑姰惉偟傑偡偑丄嬋偵傛偭偰偼偙偺壒傪昁梫偲偟側偄偨傔丄廬棃婛惢昳偱傕偙偺億僕僔儑儞偱偺昞尰偑偨傑偵弌偰偒傑偡丅傾儊乕僕儞僌僌儗僀僗傗丄僕儏僺僞乕丄僒僀儗儞僩僆僽僒僀儗儞僗側偳偑偦偆偱偡丅偁丄偁偲儅僀儚儞傾儞僪僆儞儕乕儔僽側傫偐傕壒堟揑偵偄偗偪傖偄傑偡偹丅
屄恖揑偵偼丄偙偺儌僨儖偺応崌偩偲忋偺3rd億僕僔儑儞偺曋棙偝偵夃傫偱偟傑偭偰丄偁傑傝巊偆棙揰偲昿搙傪尒弌偣側偄億僕僔儑儞偱偡偑丄4th億僕僔儑儞偲摨偠偱丄晹暘揮挷撪偱偼僈儞僈儞巊偭偰傞億僕僔儑儞側偺偱偟偨丅
傑偨帺暘偑宱尡偟偨偙偲偁傞嬋偱偡偲丄乽垽偺垾嶢乿偺傛偆側倐俁搙忋偵揮挷偟偰傑偨栠傞丄傒偨偄側嬋傪3rd仺12th仺3rd偱傗偭偨偙偲偑偁傝傑偡丅偙傟偼寢峔柺敀偐偭偨丅
偝傜偵僕儍僘偱傛偔偁傞b6搙忋揮挷傪4th仺12th偱傗偭偰傒傞偺傕堦嫽偐丠側傫偰丅傗偭偨偙偲柍偄傫偩偗偳丄偄傗偄傗寢峔柍棟偁傞偐傕側偀偝偡偑偵偙傟偼丅丅丅
側偍丄12Th億僕僔儑儞儅僀僫乕乮Fm乯偼堦売強僆乕僶乕僽儘僂偑弌偰偒傑偡偑丄儀儞僪傕懡偄偨傔丄嵞尰偼擄偟偄偱偡丅
仭偙傟埲奜偺億僕僔儑儞偵側傞偲丄僆乕僶乕僽儘僂偑昁恵偵側傝傑偡丅崱夞偼妱垽偟傑偡丅
僆乕僶乕僽儘僂偲偄偆媄弍偼丄崱擔偵帄偭偰偼偄傠傫側恖偑抦傝丄傑偨尋媶偝傟丄嫵嵽傕Tips傕憹偊丄儅僗僞乕偱偒偨恖傕憹偊偰偒偨偺偱偦傟傎偳旔偗傞懚嵼偲傕巚偄傑偣傫偑丄偦傟偱傕側偍丄婛惢昳偱偼晄埨掕側媄弍偩偲巚偄傑偡丅
妝婍傪妝偟傓傕偺偵偲偭偰偼晄埨掕側偺偼崲傞偟丄偦傟偱偼壒偺攝楍偱岺晇偟偰傒傛偆偐丄偲偄偆妏搙偐傜摿庩僠儏乕僯儞僌偲偄偆傕偺傪捛媮偟偰偒傑偟偨偑丄偙傟偑崱偺偲偙傠偺摎偊偐側丄偲傕巚偄傑偡丅
柍榑僕儍僘側偳偵偍偗傞揮挷偵偍偄偰偼僴乕儌僯僇傪岎姺偟偨傝偩偲偐偼昁梫偵側傞応崌傕偁傝傑偡偑丄婛惢昳傛傝偐偼偼傞偐偵嬋偺僥儕僩儕乕傕峀偑傞偲巚偄傑偡丅僕儍儞儖偵偍偄偰傕丅
儀儞僪偺僐儞僩儘乕儖偼昁恵偵側傝傑偡偑丄壖偵儀儞僪傪儅僗僞乕偟偨曽側傜丄1st億僕僔儑儞偱廬棃偺僼僅乕僉乕側墘憈傗揱摑揑側墘憈傪揔偊丄僽儖乕僗偵偍偄偰偼僙僇儞僪億僕僔儑儞偱廬棃偺僼傿乕儕儞僌偱妝偟傒丄摨帪偵僜僂儖僫儞僶乕側偳傕寭偹旛偊丄僕儍僘傗POPS丄壧梬嬋側偳偼3rd億僕僔儑儞偱懠偵偼弌棃側偄晹暘傪僼僅儘乕偱偒傞丅
偦傟傜偑堦杮偱丄婥暘師戞偱嬋挷傕曄偊偨傝偩偲偐偱偒傞偭偮乕偲偙傠偑椙偄偐側偀丄丄丄丄側傫偰偹丅
偪側傒偵偙偺儌僨儖堦杮偱慡Key傪昞尰偟偨偺偑偙傟偱偡丅12key3_1.mp3
仭擖庤偱偒傞偐丠仭
傕偟傕壖偵丠嫽枴偑暒偄偰帋偟偰傒偨偄側偀乣偲巚偭偨応崌丄偳偆傗偭偰庤偵擖傟偨傜椙偄偺偱偟傚偆丒丒丒
巗斕偼偝傟偰偄側偄偟丄偙傟傪婛惢昳偐傜儕乕僪傪僈僔僈僔嶍傞偺偼偐側傝偺庤娫偱偡丅丅丅丅
偦偙偱丄摿偵僴乕儌僯僇偺庬椶偵偙偩傢傝偑柍偗傟偽丄SUZUKI妝婍偺僆乕僟乕儊僀僪惢嶌偑偍摼偱偡丅
側傫偲妝婍戙懠偵1050墌亄憲椏偱傗偭偰偔傟偪傖偄傑偡傛丅
丂丂僗僘僉妝婍傊俧俷両http://www.suzuki-music.co.jp/
壖偵崱夞徯夘偟偨丄KeyG乮2nd億僕僔儑儞偱乯偺儌僨儖傪嶌偭偰傒傑偟傚偆両
嘆儊乕僇乕僒僀僩偐傜乽僆乕僟乕儊僀僪僴乕儌僯僇乿傪慖戰
嘇偛拲暥庤弴傊
嘊僆乕僟乕儊僀僪僴乕儌僯僇偛拲暥夋柺傊
嘋10儂乕儖僘傪慖戰偟傑偡丅
嘍僴乕儌僯僇偺婡庬傪慖戰偟傑偡丅崱夞偼偍帋偟偲偄偆偙偲偱堦斣埨壙側僽儖乕僗儅僗僞乕MR-250傪丅
嘐挷巕傪慖傃傑偡丅偙偙偼乽A乿傪慖傃傑偡丅KeyG傪嶌傞偨傔偵偼偙偙偐傜偄偠偭偰偄偔偺偱偡丅
嘑壒奒傪慖傃傑偡丅Special傪慖傫偱偔偩偝偄丅
嘒嬶懱揑偵壒傪巜掕偟傑偡丅夋柺偵偼A挷偺攝楍偑彂偄偰偁傝傑偡偺偱丄壓偺恾傛偆偵曄峏偟傑偡丅
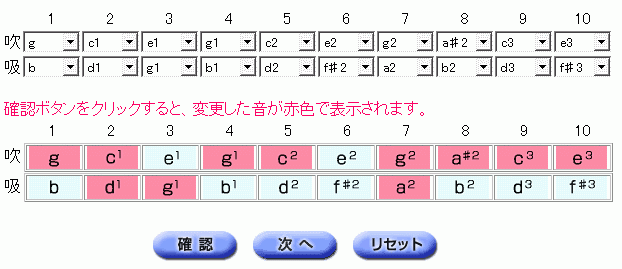
偙傟偼妋擣儃僞儞傪墴偟偨屻偱偡偑丄偙偺傛偆偵愒怓偺晹暘偑曄峏偝傟偨晹暘偱偡丅摨偠偵側偭偰偄傑偡偐丠
側偭偰偄傑偟偨傜丄師傊丅
嘓巇忋偘偱偡丅Name傪擖傟傞偐偼偛帺桼偵丅丅丅丅丅
嘔偙偙偱丄偛堄尒丄偛梫朷偺偲偙傠偵丄乽偙偺僴乕儌僯僇偼俙挷偐傜曄峏偟偰偄傑偡偑丄僉乕帺懱偼俧挷偵側傞偺偱昞帵摍丄懳墳偍婅偄偟傑偡乿偲彂偄偰偍偒傑偟傚偆丅
嘕拲暥撪梕妋擣傪偟傑偡丅壙奿偼憲椏娷傔偰4410墌偱偡両嵞搙曄峏揰側偳傪僠僃僢僋偟傑偟傚偆丅
嘖師夋柺偵峴偒丄楢棈愭側偳傪婰擖偟丄偁偲偼巜帵偵廬偭偰偔偩偝偄丅
偪側傒偵帺暘偱儕乕僪僈儕僈儕攈偼Ab偐傜嶌偭偰偄偔偺偑椙偄偱偡傛丅
偦傟偱偼偄傠偄傠偍旀傟條偱偟偨乣
2007.4.23
仭flisnuf(僼儕僗僫僼乯偺僒乕僪億僕僔儑儞傪僺僢僋傾僢僾偡傞仭
flisnuf傪巊偭偰壒傪偲偭偰傒傑偟偨丅傑偢偼偙傟傪暦偄偰偔偩偝偄丅
乵壒尮]僒儕乕僈乕僨儞
偝偰丄墘憈傪挳偄偨偲偙傠偱丄幚偼嬋拞偵僴乕儌僯僇傪僠僃儞僕偟偰墘憈偟傑偟偨丅偄偢傟傕堘偆Key偱偡丅
偙偺嬋偼4彫愡偛偲偵懎偵尵偆A-A-B-A宍懺偺嬋偱偡偑丄
嵟弶偺4彫愡[A]傪俠偺flisnuf 1st億僕僔儑儞偱丅
師偺4彫愡[A]傪俛倐偺flisnuf 3rd億僕僔儑儞偱丅
僒價偺4彫愡[B]傪俥偺flisnuf 2nd億僕僔儑儞偱丅
嵟屻偺4彫愡[A]傪俛倐偺flisnuf 3rd億僕僔儑儞偱丅
墘憈偟偰偄傑偡丅
偄偢傟傕嬋偺key偼俠偵側傝傑偡丅
傕偆堦搙椙偔暦偔偲偪傚偭偲堘偆偐側偀偲夝傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄偼偨偟偰嵟弶偵偦傟偑夝傝傑偟偨偱偟傚偆偐丅
僙僇儞僪億僕僔儑儞偺僒僂儞僪僀儊乕僕偼婛偵彸抦偺曽傕偄傞偐傕偟傟傑偣傫偹丅崱夞偼僒價偩偗偱偟偨偑暯儊儘[A]偺偲偙傠傪2nd億僕僔儑儞偱悂偔偲儀儞僪偑弌偰偒偰丄偲偨傫偵2nd億僕僔儑儞偭傐偝偑晜偒弌傑偡丅
仭崱夞偼3rd傪庢傝忋偘傞偲尵偆偙偲偱丄傑偢偼flisnuf偱峴偆3rd億僕僔儑儞儊僕儍乕偺僒僂儞僪僀儊乕僕傪斾妑偟偰傕傜偆偨傔偵偙偆偄偭偨庤朄傪偲傝傑偟偨丅
偄傢傟側偄偱暦偔偲丄1st億僕僔儑儞偲堘偄偑夝傝偵偔偄偱偡偹丅偟偐偟1st億僕僔儑儞偑悂壒偺昿搙偑崅偄偺偵懳偟偰偙偺3rd偩偲傎偲傫偳偑媧壒偵側傝丄偦偺曈偺屇媧姶偲偄偆偐丄媧偭偨姶偠偺壒偺昞尰偑偑2nd偵旕忢偵帡偰偄傑偡丅
偪傚偆偳丄1st偲2nd偺椉曽偺惈奿傪帩偭偨億僕僔儑儞偱丄墘憈偡傞嬋偵傛偭偰僲儞僼僃僀僋偱僗僩儗乕僩偵傕偄偗傞偟丄僼僃僀僋傗儀儞僪偱2nd晽側枴晅偗傕俷俲偲偄偆姶偠偱偟傚偆偐丅
偨偩丄媡傪尵偊偽丄1st掱悂偒傗偡偔偼柍偔丄2nd偵傕側傝偒傟側偄偲偄偆婍梡昻朢偝傪帩偭偰偄傑偡丅偙偺偙偲偐傜丄1st偱傕2nd偱傕悂偗側偄嬋偵懳偟偰偺3斣栚偺傾僾儘乕僠側偺偩丄偲偄偆懚嵼偺傛偆側婥偑偟偰偄傑偡丅
仭1st偱傕2nd偱傕悂偗側偄宯偺嬋傪堦嬋庢傝忋偘偰傒傑偟偨丅僗僂傿乕僩儊儌儕乕偱偡丅
偙偺嬋偼1st偱悂偔偵偼嬋挷偑岦偄偰側偔丄2nd偱悂偔堊偵偼僆乕僶乕僽儘僂昁恵偱墘憈偺擄堈搙偑崅偄偱偡丅
偱偼3rd偱偼丒丒丒丒
[壒尮]僗僁僀乕僩儊儌儕乕丂flisnuf 俧 3rd億僕僔儑儞(嬋key偼俙乯
寛偟偰娙扨偲偼偄偄傑偣傫偑丄偦傟偼嬋偑擄偟偄偐傜偱偡偹丅媄弍揑偵偼儀儞僪媄弍偑偁傟偽偙偙傑偱悂偗傑偡丅
偙偆偄偆偙偲偑弌棃偪傖偆偺偑丄3rd億僕僔儑儞儊僕儍乕偺椡側傫偩側偀偲婥偯偐偝傟傑偡丅
仭嶲峫傑偱偵丄僆乕僶乕僽儘僂偲偐傪嬱巊偟偰2nd偱悂偄偨壒尮偱偡丅崱夞偼flisnuf偱悂偄偰傑偡偑偙偺嬋偵娭偟偰偄偊偽flisnuf傕巗斕偺婛懚僠儏乕僯儞僌俢傕悂偒曽偼摨偠偱偡丅僎儘僎儘儉僘僀偱偡丅丅丅丅
3rd偺偲偒偲斾傋傞偲丄偳偪傜傕億僕僔儑儞揑側椙偝偑偁傞偲巚偄傑偡偑丄拝栚揰偼昁梫媄弍偺嵎偱偟傚偆偐丅
媄弍揑偵僆乕僶乕僽儘僂桳傝偲柍偟偲偼塤揇偺嵎偱偼側偄偱偟傚偆偐丅偦傟偩偗3rd偺傎偆偑偙偺庤偺嬋傪挧傒傗偡偄偟丄儅僗僞乕偟傗偡偄偼偢偱偡丅
[壒尮]僗僁僀乕僩儊儌儕乕丂flisnuf 俢 2nd億僕僔儑儞乮嬋Key偼俙乯
偦傟偱偼丄傑偨師夞丅